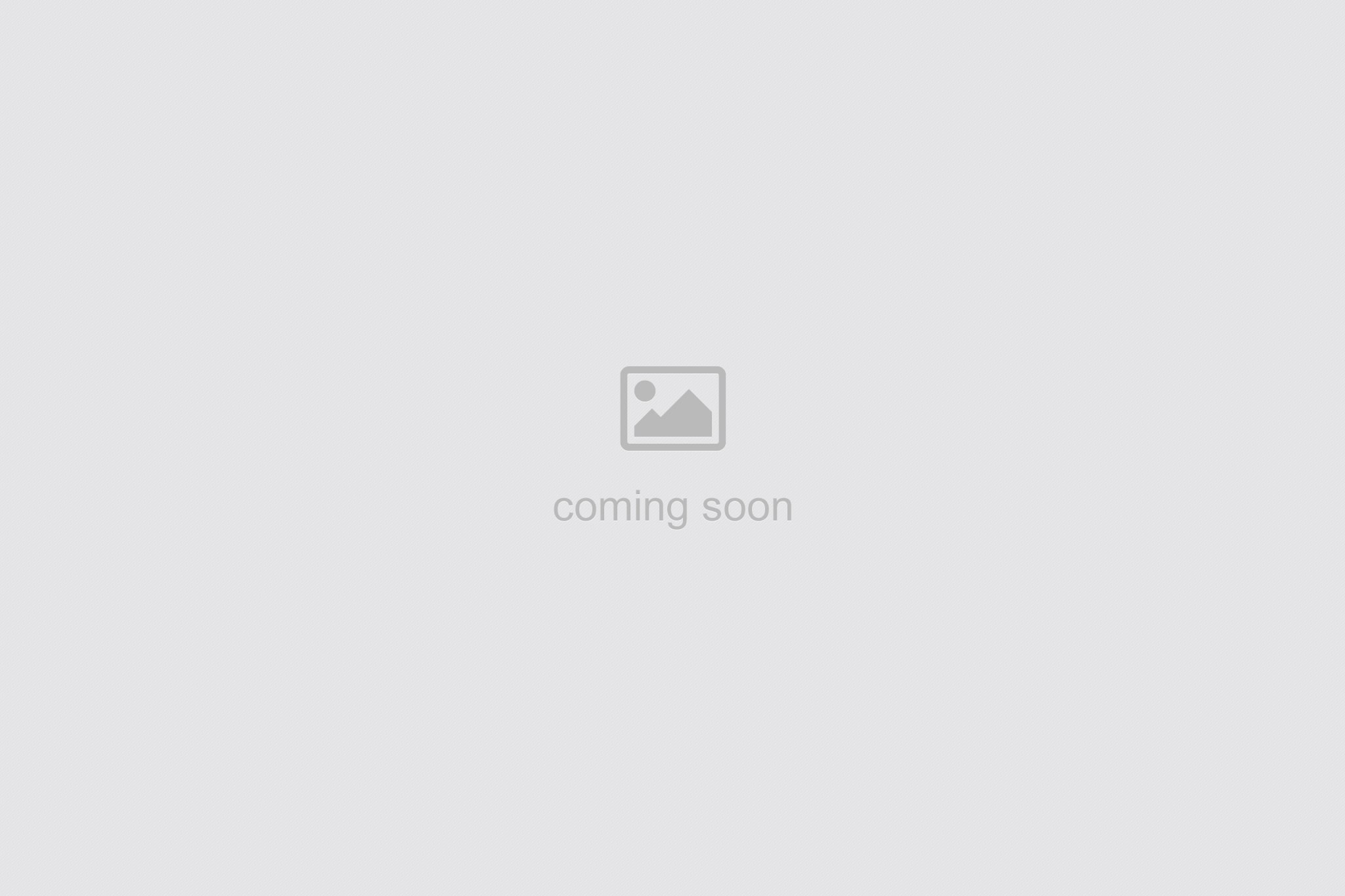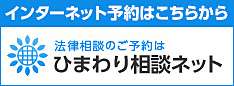適正な法曹人口に関する決議
適正な法曹人口に関する決議
2010-11-20
平成22年11月20日、当長野県弁護士会は「適正な法曹人口に関する決議」を採択いたしました。
決議内容は下記の通りです。
記
第1 決議の趣旨
当会は、政府に対し、司法試験合格者数を年間3000人程度とする政策について直ちに見直し、司法試験合格者数を段階的に削減し、弁護士人口が4万人に達した以降、これを維持するため、司法試験合格者数年間1000人程度とする法律制度の運用を求める。
第2 決議の理由
1 はじめに
当会は、本年度の日弁連会長選の最大の争点となった法曹人口問題について検討すべく関連委員会に諮問をなし、平成22年6月26日の総会後には識者を呼んで勉強会を開催すると共に修習生の給費制維持に向けての請願活動に全力を傾注してきたものであるが、その間、若手弁護士ないし司法修習生の置かれている厳しい現実がマスコミの注目するところとなっている。
当会から給費制維持の請願を受けた長野県議会は、平成22年7月2日、「必ずしも法的紛争が増加していないにもかかわらず、法曹人口の大幅な拡大が行われた結果、司法修習を終了しても法曹として自立するために必要十分な仕事や経験を積む機会が確保されない者が生じるなど、法曹の質の維持・確保が懸念されている。」とした上「よって、国においては、…、法曹の質の維持・確保を図るため適正なる法曹人口の検討を行うよう強く要請する。」との意見書を採択している。
当該意見書は、同議会において上記部分を追加して全会一致で採択したものであるが、当弁護士会としても同じ問題意識を共有しているものであり、同意見書の具体化を図るべく司法試験合格者数について検討を行うことは法律制度の改善に努力することを求められている弁護士会の使命であると共に長野県議会ないし長野県民に対する責務でもある。
2 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画について
政府の法曹人口の大幅な増員政策は、平成13年6月12日司法制度改革審議会(以下「司法審」という。)の意見書(以下「司法審意見書」という。)を受けて、平成14年3月19日閣議決定がなされた司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。)に基づき行われてきたものである。推進計画においては「現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す。」と記載されている。
3 法的需要の見込み違いについて
しかしながら、以下に述べるようにその前提とする立法事実の理解には疑問がある。
(1) 司法審のアンケート結果の」無視
まず、推進計画にいう「現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり」との認識については疑問がある。当時司法審は平成12年6月全国16地裁において総勢591名に対するアンケート調査を実施しているが、同調査の結果として、弁護士を付けるのに「苦労しなかった」は21%、「全く苦労しなかった」は65・3%であることを明らかとし、更に同調査に基づく報告書において「今回の調査の回答者では弁護士の委任率が高く、かつ、弁護士へのアクセス障害の報告も少なかった」と結論付けているからである。
司法審においても、自ら行った調査に基づくアクセス障害が少ないとの上記客観的データを分析することなく、他の客観的データを示すことなく、法的需要に十分対応することができないと結論付けているのは疑問という外ない。
なお、司法審の調査については、裁判所に辿り付けた人を対象とするものであり、辿り付けない人も存在するのであるから、必ずしも、アクセス障害がないとまでは言えないとの反論もなされている。しかし、当該調査は、アクセス障害の有無を目的として全国16の裁判所の協力を得て調査したものであるところ、裁判所に辿りつけた人に特段の障害がないとすれば、一般的に特段のアクセス障害がないものと分析することが正しい。しかも、その後、弁護士数が約1・7倍増え、弁護士に辿り着ける客観的可能性が高まっているにもかかわらず事件数自体が増えていないとの事実は、推進計画策定当時にも増して、アクセス障害の問題は少なくなっており、法的需要が必ずしも大きくないことの証左でもある。
(2) 法的需要の増大はない
次に、推進計画が予測した「今後の法的需要の増大」は実現しておらず、これまた前提を欠く議論がなされたものと言わざるを得ない。
すなわち、事件数はその後、約6%減少しているからである。最高裁判所の司法統計によれば、平成12年度の総新受事件数(民事・行政事件、刑事事件等、家事事件及び少年事件の件数。但し、刑事事件等及び少年事件は人数)は553万7154件であり、平成20年度の総事件件数は443万2986件となっている。この内、統計数値の採用基準の変更により雑事件が77万件減少していることを考慮すると、その実質的な減少数は33万件であり、その減少割合は約6%となる。
また、地裁民事の訴訟事件についても、平成12年度は18万4246件であったが、その後漸次低減し、平成17年度には15万4380件まで低下している。その後、過払事件の急増により平成20年度の事件総数は約22万件に達しているものの、その約半分を過払金返還請求事件が占めていることから、実質的には減少傾向は現在も続いていると見られる。なお、過払金返還請求事件は貸金業法の抜本的改正及び消費者金融業者の相次ぐ撤退等により早晩収束するものと予測されるが、過払金事件を除いた10万件との事件数は平成初期の事件数と同じである。
4 法曹人口の現状について
司法審意見書では、日本における法曹人口を当面フランス並にすることが急務であるとしているが、フランスでは、弁護士が税理士業務等日本における隣接法律関係業務を含めて行っており、日本における法曹人口を検討する場合には司法書士・税理士等の隣接法律関係専門職の存在を考慮することが不可欠であるにもかかわらず、この視点が欠落している。ちなみに、隣接法律関係専門職を含めて法曹一人当たりの国民数を平成21年において比較すると、日本が773名なのに対し、フランスは1275名であり、フランスは日本の6割程度しか法曹がいないのである。
平成12年4月時点における弁護士数は1万7126人であり、平成22年4月時点における弁護士数は2万8828人とこの10年間で約68%もの増加が図られている。しかも、平成15年認定司法書士制度が新設され、平成21年4月現在司法書士の62%にあたる1万2251人が認定司法書士登録をなし、平成20年度においては、9万1437件の簡裁代理権業務及び53万6622件の裁判外和解手続に関与するに至っているという事実も認識する必要がある。
一方、裁判官及び検察官の数は、平成11年度合計3447人から平成21年度合計4539人と10年間に32%しか増えておらず、司法基盤の拡大は、不均衡な形で行われてしまっているし、近時合格者の1割程度しか任官しておらず、その不均衡は一層拡大しつつある。
5 法曹人口急増による弊害について
法曹人口急増による弊害が立場の弱い司法修習生、司法試験受験及び若手弁護士を直撃している。
⑴ 就職問題とOJTの機会の喪失
法的需要がないのに弁護士の急増が図られた結果、平成18年ころから新人弁護士の就職難という事態が発生し、年々深刻度を増しており、司法修習終了時の弁護士未登録者は、平成19年度は新旧60期生で102人、平成20年度の新旧61期生で122人、平成21年度の新旧62期生で184人に上り、平成22年度の内定率は前年同月比10%以上悪化していることからして、司法修習終了時に1割以上の司法修習生が登録できない見込みである。
この傾向は今後ますます深刻度を増してゆくものと推測されると共にオンザジョブトレーニングを欲しながらも勤務先を得られず、登録後直ちに独立して業務を行わざるを得ない弁護士の増加が余儀なくされることが懸念される。
ちなみに、当会では、弁護士が複数の事務所が平成15年では8事務所であったところ、平成21年度では22事務所と急増しており、平成22年度には更に約10事務所が増える予定である。これは、日弁連及び当会執行部の要請もあり、勤務弁護士を受け入れたことに主たる理由があると考えられ、近い将来,受け入れが実際上不可能になることが確実に予測される。
また、この点について、平成15年度(4月1日現在・以下同じ)114名であった会員数が、同18年度には126名、同20年度には146名、同22年度には164名となり、平成23年度には更に20名が増加することが確実であり、その後も当面年間15〜20名程度増加することが予測されることも考慮されるべきである。
⑵ 司法修習生の借金問題
一方、司法修習を終った時点で、司法修習生は、多い者で1200万円、平均でも318万円もの負債を負っている事態にあることも判明し、「金持ちしか法律家になれない」との批判を受けるに至っている。弁護士になれば相応の収入が確保されるのであれば多少の借入があったとしても返済可能であろうが、後述の収入の低下傾向に見られるように、必ずしも経済的自立が叶わないとなると、多額の借財を負うことへの不安感を有するのは当然のことである。
⑶ 勤務弁護士の年収の低下
勤務弁護士の平均年収は平成18年度から平成20年度までの賃金構造基本統計調査(賃金センサス)によれば約800万円程度で推移していたところ、平成21年度は680万円(平均年齢36・4才・調査人数1350名)と低下しており、勤務できたからと言って必ずしも経済的に余裕があるとも言えない。弁護士の場合、通常月額5万円〜7万円程度の様々な名目による会費の負担があるからである。同調査における大学・大学院卒の平均年収は674万円であり、勤務弁護士報酬は実質的には平均以下ということである。
⑷ 法曹志望者の減少
このような弁護士業界を巡る厳しい現実が明らかになるにつれ、法科大学院の志願者は著しく減少し、平成15年には延べ人数で5万9393人いた法科大学院適正試験志願者が平成22年度には1万6469人と72%も減少している。加えて、法科大学院への社会人入学者の割合も平成16年度の48・4%から29・8%に低下しており、法曹の魅力が喪失し、多様な優秀なる人材が法曹を目指さなくなったのではないかとの危惧が現実化している。
⑸ マスコミによる問題点の指摘
この事態を反映して、平成22年4月17日付毎日新聞は「金持ちしか法律家になれない」との記事を掲載し、平成22年5月号の東洋経済は各種データを示して法的需要が増えていないのに弁護士が急増している状況を伝え、平成22年7月19日付朝日新聞はその一面、二面で「弁護士になったけれど」「苦悩する弁護士の卵」との記事を掲載した外、弁護士がコンビニでアルバイトをしている状況を伝え、写真週刊誌を含めマスコミが広く若手弁護士の窮状を伝えるに至っている。
なお、NHKは9月4日「急増する弁護士トラブル」と題する特集をし、弁護士が急増する中、弁護士による被害が急増していることを伝えるに至っている。
6 法的需要に見合った法曹人口を目指すべきことについて
このような深刻な事態を改善するためには、法的需要に見合った法曹人口の増加を図る必要があることは自明の理である。
これに対しては、司法審意見書は「実際に社会の様々な分野で活躍する法曹の数は社会の要請に基づいて市場原理によって決定されるものであり、新司法試験の合格者数を年間3,000人とすることは、あくまで『計画的にできるだけ早期に』達成すべき目標であって、上限を意味するものではないことに留意する必要がある。」と述べる。
法の支配の担い手は多いに越したことはなく、実際に必要とされる法曹数は市場原理で淘汰されてしかるべきであるとの見解である。
しかし、そもそも,3000人説の根拠は、隣接士業を考慮することなく単純にフランス並の法曹人口を目指すとした根拠薄弱なものに過ぎないし、行きすぎた市場原理が決して社会に利益をもたらさないことは,いわゆるリーマンショックでも明らかになっている。すでに,競争原理により大幅な弁護士増員が実現したアメリカにおいては,「訴訟社会」という病理現象が発生しており,弁護士と市民が対立関係になっている。
また、司法審の述べるとおり、需要を決めるのは,国民であるとすれば,平成年間に入っての訴訟件数の減少は,あふれるばかりの弁護士を求めていないことの徴表ともいえるものである。
加えて、市場原理による淘汰論は弁護士が高度な学識を有する専門家であり、弁護士法により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、そのために法律制度等の改善に努力することを無償で義務付けられていることを看過したものである。
現在法曹になるためには大学卒業後、2年ないし3年間法科大学院に通い、合格率3割の試験に合格したとしても、更に1年の司法修習を終えることが要件とされ、司法修習期間中は修習専念義務が課されており、通常5年間にわたるかなり密度の高い勉学が要求される正に専門職なのである。このように時間と費用をかけて育成した法曹資格者(弁護士)を自由競争による淘汰に任せることは社会的無駄であると言わざるを得ないし、このように多額な経費と時間をかけて資格を得ても、淘汰される危険に晒されているとなると優秀なる人材が司法界に来なくなるおそれがあり、そのおそれは現実化している。
司法審意見書は、弁護士を社会生活上の医師である旨位置付けているが、医師については自由競争による淘汰が予定されていないことに異論はあるまい。どんな社会においても専門家の関与が必要な法的業務は一定の量に限られているのであり、必要に応じて養成すべきものと思料する。
また、自由競争の結果、経済的基盤が脆弱化した弁護士に弁護士法の求める無償の公益的活動を期待することは困難である。現在、日弁連は登録5年未満の弁護士の会費の一部免除をしているが、月額5万円〜7万円に上る会費が公益的活動の原資となっているのであって、会費の負担に耐えられない弁護士が今後益々増加することが容易に推測されるのである。
そもそも、自由競争原理は、顧客に商品に対する品質判断能力が必要とされるが、一般国民が弁護士を必要とする事態は一生に一度あるか、ないかであり、自由競争原理が適正に作用する場面とは言えない。
7 適正な法曹人口について
そこで、適正なる法曹人口が何名であるかであるが、法的需要に応じた法曹人口が措定されるべきである。日弁連は、10年後に5万人規模の弁護士人口を安定的に吸収しうるだけの法的ニーズを予測することは困難であると結論付けている(平成20年3月7日付弁護士業務推進センター法的ニーズ、法曹人口調査検討チーム作成報告書)。
日本社会は成熟度を増し、外国に比して安定していることから必ずしも紛争が増加するとも言えないこと、20年後の日本の人口は国立社会保障・人口問題研究所の予測からすると、平成21年が1億2717万人であるところ、平成42年には1億1522万人と約1割の減少が認められ、20年後の紛争も1割程度減少すると推測されるからである。
なお、平成22年5月に当会で行った会員向けアンケートの結果によれば、適正弁護士人口は、その回答を加重平均すると3万3000名との数値が出ている。この数値は、平成20年度に当会が行った法曹適正人口のアンケート結果の多数意見である「弁護士は多少足りない。」との認識に合致するものである。ただ、当会は本庁と6支部からなる7つの在住会からなっており、その在住会毎に弁護士一人あたりの人数には約2・5倍の開きがあり、その具体的認識が必ずしも一致しないところではあるが、司法書士、税理士等の隣接士業の存在を考慮するならば、精々幅をもって考えても、現在の約3割増にあたる4万人程度を適正人数とするのが相当である。
また、平成22年5月の会員アンケートによれば、年間合格者数については加重平均すると1300名となり、一方で適正な法曹人口を3万3000人としたこととの整合性が問題になるが、現状2000名を超える法曹養成が行われていることからして、直ちに大幅引き下げには躊躇を感じるとの会員の意識を反映したものと推測される。
ところで、現状の法曹人口を維持するに足る年間合格者が何名であるかを確認しておくに、昭和35年(1960年)以降平成2年(1990年)まで、年間司法試験合格者500人時代が続いていることから、今後20年間に廃業するであろう弁護士は任官者からの登録替えを含めても1万人未満、年間500人に満たないものであり、今後20年間は500人の採用をしてゆけば、平成22年4月1日現在の弁護士人口2万8820人を維持できることになる。
また、現在登録している弁護士の年齢構成を見ると平成2009年度版弁護士白書によると80才以上の会員が1074人、70才代の会員が2693人、60才代の会員が4030人であり、弁護士はかなり高齢になっても弁護士登録をしていることが看取される。50才代の会員は4225人であり、50才代の半数及び60才代の弁護士全員が今後20年間に廃業すると仮定すれば、この20年間に予測される登録抹消者数は1万人・年間500人程度と予測される。
一方、平成22年4月時点の弁護士人口2万8828人を当面の目標とする4万人の弁護士人口に到達せしめるためには、年間合格者を現状の年間2000人程度から平成23年以降段階的に1000人程度とする制度構築がなされるべきものである。
今後、2000人合格時代が続けば、5〜6年後には弁護士人口は4万人に達することになるが、4万人到達後直ちに合格者数を半減せしめるよりも、段階的に合格者を徐々に減らしていった方が現在法曹養成の中核を担っている法科大学院にとっても適応しやすいと言える。このまま2000人もの合格者を生み出し続けることは、就職問題を一層深刻化せしめ、若手の法曹離れを加速させることは必然であり、賢明な方策とは言い難い。
8 法科大学院を巡る問題について
まず、これは言うまでもないことであるが、法曹人口問題は法曹養成制度の有り方との関係を抜きにしては考えられないところ、法曹養成は法的需要に見合った適正な法曹人口を生み出すために行われるべきものであり、法科大学院の存続を図るために過剰な法曹養成が行われるべきものではない。
この問題は、地域の子弟に法曹になる機会を実質的に保障せしめる見地からの法科大学院の全国適正配置の問題の一環として考えられるべきであるが、信州大学法科大学院のように長野県に一つしかなく、地域司法の充実を目指し当会をも含めた地域ぐるみの支援を受けているだけではなく、多様な人材を確保するという本来の司法改革の理念に沿って未修者教育に力を注いでいる法科大学院は残されるべきであるし、そのために当弁護士会としても全力を傾注する所存であるし、実際にも多大な協力を行ってきたことを自負しているものである。
もちろん、現状の2000人なり、将来的な3000人なりの合格者を前提として入学してきた法科大学生の保護も考える必要があるところであり、その意味では直ちに1000人への削減を求めるものではなく、平成23年度以降段階的に削減を行い、弁護士人口が4万人に達した以降、これを維持するため、司法試験合格者数年間1000人程度とする法律制度の運用を求めるものである。
この問題については、合格者を絞ると地方の法科大学院は立ち行かないのではないかとの危惧も指摘されている。しかし、平成22年度の司法試験合格者について見れば、地方の法科大学院生の中にも相応の成績で合格している者もおり、法科大学院自身の努力次第で対応可能な部分もあると言え、その危惧を過大視する必要はない。
9 おわりに
本決議に年間1000人程度という数字を明記することについては、弁護士会が司法改革に消極に転じたとの印象を与えかねないとの危惧から反対する意見もあるが、現在弁護士会に求められているのは、国民のため、長期的な視野に立った法曹養成制度の概要を示すことなのであり、将来的なビジョンを示すことなく、具体的な制度設計は不可能である。
4万人達成後、年間1000人としても、平成40年ころまでは500人ずつ弁護士は増えてゆくのであり、司法改革が求めた弁護士数の増加は確実に果たされるのである。
長野県弁護士会は、県内に多くの山間部等を抱えており、特に司法アクセスを改善せしめる責務を負っているものであるが、適正なる法曹人口を実現せしめる中において、長野県民があまねく法的サービスを受けられるように今後とも過疎偏在解消に向けて努力を惜しまない所存である。
目先の利害に囚われることなく、将来の司法制度のあり方を考え国民に提言するのが、弁護士法1条において、法律制度の改善に努力することを使命とされた弁護士の責務であると信じる。
決議内容は下記の通りです。
記
第1 決議の趣旨
当会は、政府に対し、司法試験合格者数を年間3000人程度とする政策について直ちに見直し、司法試験合格者数を段階的に削減し、弁護士人口が4万人に達した以降、これを維持するため、司法試験合格者数年間1000人程度とする法律制度の運用を求める。
第2 決議の理由
1 はじめに
当会は、本年度の日弁連会長選の最大の争点となった法曹人口問題について検討すべく関連委員会に諮問をなし、平成22年6月26日の総会後には識者を呼んで勉強会を開催すると共に修習生の給費制維持に向けての請願活動に全力を傾注してきたものであるが、その間、若手弁護士ないし司法修習生の置かれている厳しい現実がマスコミの注目するところとなっている。
当会から給費制維持の請願を受けた長野県議会は、平成22年7月2日、「必ずしも法的紛争が増加していないにもかかわらず、法曹人口の大幅な拡大が行われた結果、司法修習を終了しても法曹として自立するために必要十分な仕事や経験を積む機会が確保されない者が生じるなど、法曹の質の維持・確保が懸念されている。」とした上「よって、国においては、…、法曹の質の維持・確保を図るため適正なる法曹人口の検討を行うよう強く要請する。」との意見書を採択している。
当該意見書は、同議会において上記部分を追加して全会一致で採択したものであるが、当弁護士会としても同じ問題意識を共有しているものであり、同意見書の具体化を図るべく司法試験合格者数について検討を行うことは法律制度の改善に努力することを求められている弁護士会の使命であると共に長野県議会ないし長野県民に対する責務でもある。
2 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画について
政府の法曹人口の大幅な増員政策は、平成13年6月12日司法制度改革審議会(以下「司法審」という。)の意見書(以下「司法審意見書」という。)を受けて、平成14年3月19日閣議決定がなされた司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。)に基づき行われてきたものである。推進計画においては「現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す。」と記載されている。
3 法的需要の見込み違いについて
しかしながら、以下に述べるようにその前提とする立法事実の理解には疑問がある。
(1) 司法審のアンケート結果の」無視
まず、推進計画にいう「現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり」との認識については疑問がある。当時司法審は平成12年6月全国16地裁において総勢591名に対するアンケート調査を実施しているが、同調査の結果として、弁護士を付けるのに「苦労しなかった」は21%、「全く苦労しなかった」は65・3%であることを明らかとし、更に同調査に基づく報告書において「今回の調査の回答者では弁護士の委任率が高く、かつ、弁護士へのアクセス障害の報告も少なかった」と結論付けているからである。
司法審においても、自ら行った調査に基づくアクセス障害が少ないとの上記客観的データを分析することなく、他の客観的データを示すことなく、法的需要に十分対応することができないと結論付けているのは疑問という外ない。
なお、司法審の調査については、裁判所に辿り付けた人を対象とするものであり、辿り付けない人も存在するのであるから、必ずしも、アクセス障害がないとまでは言えないとの反論もなされている。しかし、当該調査は、アクセス障害の有無を目的として全国16の裁判所の協力を得て調査したものであるところ、裁判所に辿りつけた人に特段の障害がないとすれば、一般的に特段のアクセス障害がないものと分析することが正しい。しかも、その後、弁護士数が約1・7倍増え、弁護士に辿り着ける客観的可能性が高まっているにもかかわらず事件数自体が増えていないとの事実は、推進計画策定当時にも増して、アクセス障害の問題は少なくなっており、法的需要が必ずしも大きくないことの証左でもある。
(2) 法的需要の増大はない
次に、推進計画が予測した「今後の法的需要の増大」は実現しておらず、これまた前提を欠く議論がなされたものと言わざるを得ない。
すなわち、事件数はその後、約6%減少しているからである。最高裁判所の司法統計によれば、平成12年度の総新受事件数(民事・行政事件、刑事事件等、家事事件及び少年事件の件数。但し、刑事事件等及び少年事件は人数)は553万7154件であり、平成20年度の総事件件数は443万2986件となっている。この内、統計数値の採用基準の変更により雑事件が77万件減少していることを考慮すると、その実質的な減少数は33万件であり、その減少割合は約6%となる。
また、地裁民事の訴訟事件についても、平成12年度は18万4246件であったが、その後漸次低減し、平成17年度には15万4380件まで低下している。その後、過払事件の急増により平成20年度の事件総数は約22万件に達しているものの、その約半分を過払金返還請求事件が占めていることから、実質的には減少傾向は現在も続いていると見られる。なお、過払金返還請求事件は貸金業法の抜本的改正及び消費者金融業者の相次ぐ撤退等により早晩収束するものと予測されるが、過払金事件を除いた10万件との事件数は平成初期の事件数と同じである。
4 法曹人口の現状について
司法審意見書では、日本における法曹人口を当面フランス並にすることが急務であるとしているが、フランスでは、弁護士が税理士業務等日本における隣接法律関係業務を含めて行っており、日本における法曹人口を検討する場合には司法書士・税理士等の隣接法律関係専門職の存在を考慮することが不可欠であるにもかかわらず、この視点が欠落している。ちなみに、隣接法律関係専門職を含めて法曹一人当たりの国民数を平成21年において比較すると、日本が773名なのに対し、フランスは1275名であり、フランスは日本の6割程度しか法曹がいないのである。
平成12年4月時点における弁護士数は1万7126人であり、平成22年4月時点における弁護士数は2万8828人とこの10年間で約68%もの増加が図られている。しかも、平成15年認定司法書士制度が新設され、平成21年4月現在司法書士の62%にあたる1万2251人が認定司法書士登録をなし、平成20年度においては、9万1437件の簡裁代理権業務及び53万6622件の裁判外和解手続に関与するに至っているという事実も認識する必要がある。
一方、裁判官及び検察官の数は、平成11年度合計3447人から平成21年度合計4539人と10年間に32%しか増えておらず、司法基盤の拡大は、不均衡な形で行われてしまっているし、近時合格者の1割程度しか任官しておらず、その不均衡は一層拡大しつつある。
5 法曹人口急増による弊害について
法曹人口急増による弊害が立場の弱い司法修習生、司法試験受験及び若手弁護士を直撃している。
⑴ 就職問題とOJTの機会の喪失
法的需要がないのに弁護士の急増が図られた結果、平成18年ころから新人弁護士の就職難という事態が発生し、年々深刻度を増しており、司法修習終了時の弁護士未登録者は、平成19年度は新旧60期生で102人、平成20年度の新旧61期生で122人、平成21年度の新旧62期生で184人に上り、平成22年度の内定率は前年同月比10%以上悪化していることからして、司法修習終了時に1割以上の司法修習生が登録できない見込みである。
この傾向は今後ますます深刻度を増してゆくものと推測されると共にオンザジョブトレーニングを欲しながらも勤務先を得られず、登録後直ちに独立して業務を行わざるを得ない弁護士の増加が余儀なくされることが懸念される。
ちなみに、当会では、弁護士が複数の事務所が平成15年では8事務所であったところ、平成21年度では22事務所と急増しており、平成22年度には更に約10事務所が増える予定である。これは、日弁連及び当会執行部の要請もあり、勤務弁護士を受け入れたことに主たる理由があると考えられ、近い将来,受け入れが実際上不可能になることが確実に予測される。
また、この点について、平成15年度(4月1日現在・以下同じ)114名であった会員数が、同18年度には126名、同20年度には146名、同22年度には164名となり、平成23年度には更に20名が増加することが確実であり、その後も当面年間15〜20名程度増加することが予測されることも考慮されるべきである。
⑵ 司法修習生の借金問題
一方、司法修習を終った時点で、司法修習生は、多い者で1200万円、平均でも318万円もの負債を負っている事態にあることも判明し、「金持ちしか法律家になれない」との批判を受けるに至っている。弁護士になれば相応の収入が確保されるのであれば多少の借入があったとしても返済可能であろうが、後述の収入の低下傾向に見られるように、必ずしも経済的自立が叶わないとなると、多額の借財を負うことへの不安感を有するのは当然のことである。
⑶ 勤務弁護士の年収の低下
勤務弁護士の平均年収は平成18年度から平成20年度までの賃金構造基本統計調査(賃金センサス)によれば約800万円程度で推移していたところ、平成21年度は680万円(平均年齢36・4才・調査人数1350名)と低下しており、勤務できたからと言って必ずしも経済的に余裕があるとも言えない。弁護士の場合、通常月額5万円〜7万円程度の様々な名目による会費の負担があるからである。同調査における大学・大学院卒の平均年収は674万円であり、勤務弁護士報酬は実質的には平均以下ということである。
⑷ 法曹志望者の減少
このような弁護士業界を巡る厳しい現実が明らかになるにつれ、法科大学院の志願者は著しく減少し、平成15年には延べ人数で5万9393人いた法科大学院適正試験志願者が平成22年度には1万6469人と72%も減少している。加えて、法科大学院への社会人入学者の割合も平成16年度の48・4%から29・8%に低下しており、法曹の魅力が喪失し、多様な優秀なる人材が法曹を目指さなくなったのではないかとの危惧が現実化している。
⑸ マスコミによる問題点の指摘
この事態を反映して、平成22年4月17日付毎日新聞は「金持ちしか法律家になれない」との記事を掲載し、平成22年5月号の東洋経済は各種データを示して法的需要が増えていないのに弁護士が急増している状況を伝え、平成22年7月19日付朝日新聞はその一面、二面で「弁護士になったけれど」「苦悩する弁護士の卵」との記事を掲載した外、弁護士がコンビニでアルバイトをしている状況を伝え、写真週刊誌を含めマスコミが広く若手弁護士の窮状を伝えるに至っている。
なお、NHKは9月4日「急増する弁護士トラブル」と題する特集をし、弁護士が急増する中、弁護士による被害が急増していることを伝えるに至っている。
6 法的需要に見合った法曹人口を目指すべきことについて
このような深刻な事態を改善するためには、法的需要に見合った法曹人口の増加を図る必要があることは自明の理である。
これに対しては、司法審意見書は「実際に社会の様々な分野で活躍する法曹の数は社会の要請に基づいて市場原理によって決定されるものであり、新司法試験の合格者数を年間3,000人とすることは、あくまで『計画的にできるだけ早期に』達成すべき目標であって、上限を意味するものではないことに留意する必要がある。」と述べる。
法の支配の担い手は多いに越したことはなく、実際に必要とされる法曹数は市場原理で淘汰されてしかるべきであるとの見解である。
しかし、そもそも,3000人説の根拠は、隣接士業を考慮することなく単純にフランス並の法曹人口を目指すとした根拠薄弱なものに過ぎないし、行きすぎた市場原理が決して社会に利益をもたらさないことは,いわゆるリーマンショックでも明らかになっている。すでに,競争原理により大幅な弁護士増員が実現したアメリカにおいては,「訴訟社会」という病理現象が発生しており,弁護士と市民が対立関係になっている。
また、司法審の述べるとおり、需要を決めるのは,国民であるとすれば,平成年間に入っての訴訟件数の減少は,あふれるばかりの弁護士を求めていないことの徴表ともいえるものである。
加えて、市場原理による淘汰論は弁護士が高度な学識を有する専門家であり、弁護士法により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、そのために法律制度等の改善に努力することを無償で義務付けられていることを看過したものである。
現在法曹になるためには大学卒業後、2年ないし3年間法科大学院に通い、合格率3割の試験に合格したとしても、更に1年の司法修習を終えることが要件とされ、司法修習期間中は修習専念義務が課されており、通常5年間にわたるかなり密度の高い勉学が要求される正に専門職なのである。このように時間と費用をかけて育成した法曹資格者(弁護士)を自由競争による淘汰に任せることは社会的無駄であると言わざるを得ないし、このように多額な経費と時間をかけて資格を得ても、淘汰される危険に晒されているとなると優秀なる人材が司法界に来なくなるおそれがあり、そのおそれは現実化している。
司法審意見書は、弁護士を社会生活上の医師である旨位置付けているが、医師については自由競争による淘汰が予定されていないことに異論はあるまい。どんな社会においても専門家の関与が必要な法的業務は一定の量に限られているのであり、必要に応じて養成すべきものと思料する。
また、自由競争の結果、経済的基盤が脆弱化した弁護士に弁護士法の求める無償の公益的活動を期待することは困難である。現在、日弁連は登録5年未満の弁護士の会費の一部免除をしているが、月額5万円〜7万円に上る会費が公益的活動の原資となっているのであって、会費の負担に耐えられない弁護士が今後益々増加することが容易に推測されるのである。
そもそも、自由競争原理は、顧客に商品に対する品質判断能力が必要とされるが、一般国民が弁護士を必要とする事態は一生に一度あるか、ないかであり、自由競争原理が適正に作用する場面とは言えない。
7 適正な法曹人口について
そこで、適正なる法曹人口が何名であるかであるが、法的需要に応じた法曹人口が措定されるべきである。日弁連は、10年後に5万人規模の弁護士人口を安定的に吸収しうるだけの法的ニーズを予測することは困難であると結論付けている(平成20年3月7日付弁護士業務推進センター法的ニーズ、法曹人口調査検討チーム作成報告書)。
日本社会は成熟度を増し、外国に比して安定していることから必ずしも紛争が増加するとも言えないこと、20年後の日本の人口は国立社会保障・人口問題研究所の予測からすると、平成21年が1億2717万人であるところ、平成42年には1億1522万人と約1割の減少が認められ、20年後の紛争も1割程度減少すると推測されるからである。
なお、平成22年5月に当会で行った会員向けアンケートの結果によれば、適正弁護士人口は、その回答を加重平均すると3万3000名との数値が出ている。この数値は、平成20年度に当会が行った法曹適正人口のアンケート結果の多数意見である「弁護士は多少足りない。」との認識に合致するものである。ただ、当会は本庁と6支部からなる7つの在住会からなっており、その在住会毎に弁護士一人あたりの人数には約2・5倍の開きがあり、その具体的認識が必ずしも一致しないところではあるが、司法書士、税理士等の隣接士業の存在を考慮するならば、精々幅をもって考えても、現在の約3割増にあたる4万人程度を適正人数とするのが相当である。
また、平成22年5月の会員アンケートによれば、年間合格者数については加重平均すると1300名となり、一方で適正な法曹人口を3万3000人としたこととの整合性が問題になるが、現状2000名を超える法曹養成が行われていることからして、直ちに大幅引き下げには躊躇を感じるとの会員の意識を反映したものと推測される。
ところで、現状の法曹人口を維持するに足る年間合格者が何名であるかを確認しておくに、昭和35年(1960年)以降平成2年(1990年)まで、年間司法試験合格者500人時代が続いていることから、今後20年間に廃業するであろう弁護士は任官者からの登録替えを含めても1万人未満、年間500人に満たないものであり、今後20年間は500人の採用をしてゆけば、平成22年4月1日現在の弁護士人口2万8820人を維持できることになる。
また、現在登録している弁護士の年齢構成を見ると平成2009年度版弁護士白書によると80才以上の会員が1074人、70才代の会員が2693人、60才代の会員が4030人であり、弁護士はかなり高齢になっても弁護士登録をしていることが看取される。50才代の会員は4225人であり、50才代の半数及び60才代の弁護士全員が今後20年間に廃業すると仮定すれば、この20年間に予測される登録抹消者数は1万人・年間500人程度と予測される。
一方、平成22年4月時点の弁護士人口2万8828人を当面の目標とする4万人の弁護士人口に到達せしめるためには、年間合格者を現状の年間2000人程度から平成23年以降段階的に1000人程度とする制度構築がなされるべきものである。
今後、2000人合格時代が続けば、5〜6年後には弁護士人口は4万人に達することになるが、4万人到達後直ちに合格者数を半減せしめるよりも、段階的に合格者を徐々に減らしていった方が現在法曹養成の中核を担っている法科大学院にとっても適応しやすいと言える。このまま2000人もの合格者を生み出し続けることは、就職問題を一層深刻化せしめ、若手の法曹離れを加速させることは必然であり、賢明な方策とは言い難い。
8 法科大学院を巡る問題について
まず、これは言うまでもないことであるが、法曹人口問題は法曹養成制度の有り方との関係を抜きにしては考えられないところ、法曹養成は法的需要に見合った適正な法曹人口を生み出すために行われるべきものであり、法科大学院の存続を図るために過剰な法曹養成が行われるべきものではない。
この問題は、地域の子弟に法曹になる機会を実質的に保障せしめる見地からの法科大学院の全国適正配置の問題の一環として考えられるべきであるが、信州大学法科大学院のように長野県に一つしかなく、地域司法の充実を目指し当会をも含めた地域ぐるみの支援を受けているだけではなく、多様な人材を確保するという本来の司法改革の理念に沿って未修者教育に力を注いでいる法科大学院は残されるべきであるし、そのために当弁護士会としても全力を傾注する所存であるし、実際にも多大な協力を行ってきたことを自負しているものである。
もちろん、現状の2000人なり、将来的な3000人なりの合格者を前提として入学してきた法科大学生の保護も考える必要があるところであり、その意味では直ちに1000人への削減を求めるものではなく、平成23年度以降段階的に削減を行い、弁護士人口が4万人に達した以降、これを維持するため、司法試験合格者数年間1000人程度とする法律制度の運用を求めるものである。
この問題については、合格者を絞ると地方の法科大学院は立ち行かないのではないかとの危惧も指摘されている。しかし、平成22年度の司法試験合格者について見れば、地方の法科大学院生の中にも相応の成績で合格している者もおり、法科大学院自身の努力次第で対応可能な部分もあると言え、その危惧を過大視する必要はない。
9 おわりに
本決議に年間1000人程度という数字を明記することについては、弁護士会が司法改革に消極に転じたとの印象を与えかねないとの危惧から反対する意見もあるが、現在弁護士会に求められているのは、国民のため、長期的な視野に立った法曹養成制度の概要を示すことなのであり、将来的なビジョンを示すことなく、具体的な制度設計は不可能である。
4万人達成後、年間1000人としても、平成40年ころまでは500人ずつ弁護士は増えてゆくのであり、司法改革が求めた弁護士数の増加は確実に果たされるのである。
長野県弁護士会は、県内に多くの山間部等を抱えており、特に司法アクセスを改善せしめる責務を負っているものであるが、適正なる法曹人口を実現せしめる中において、長野県民があまねく法的サービスを受けられるように今後とも過疎偏在解消に向けて努力を惜しまない所存である。
目先の利害に囚われることなく、将来の司法制度のあり方を考え国民に提言するのが、弁護士法1条において、法律制度の改善に努力することを使命とされた弁護士の責務であると信じる。
平成22年11月20日臨時総会決議
長野県弁護士会